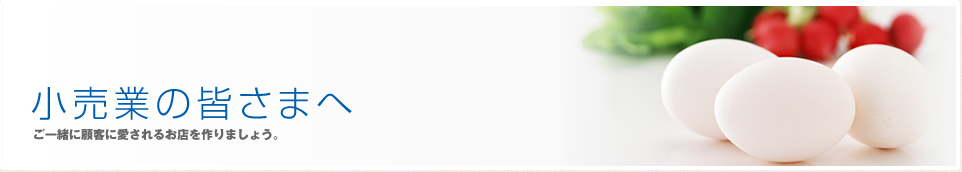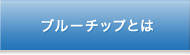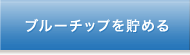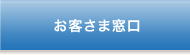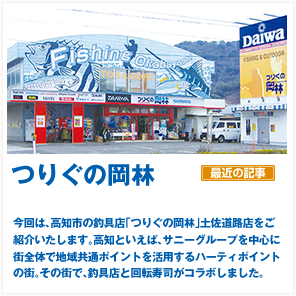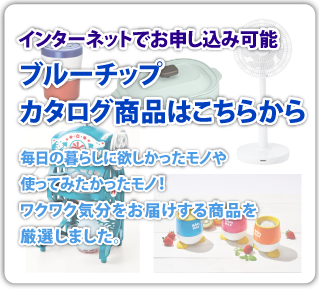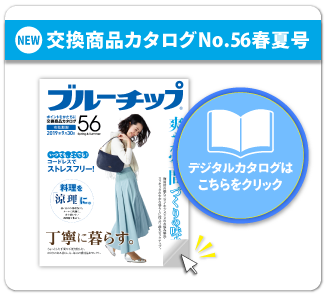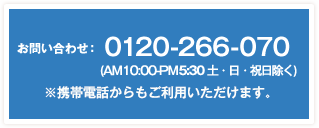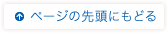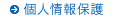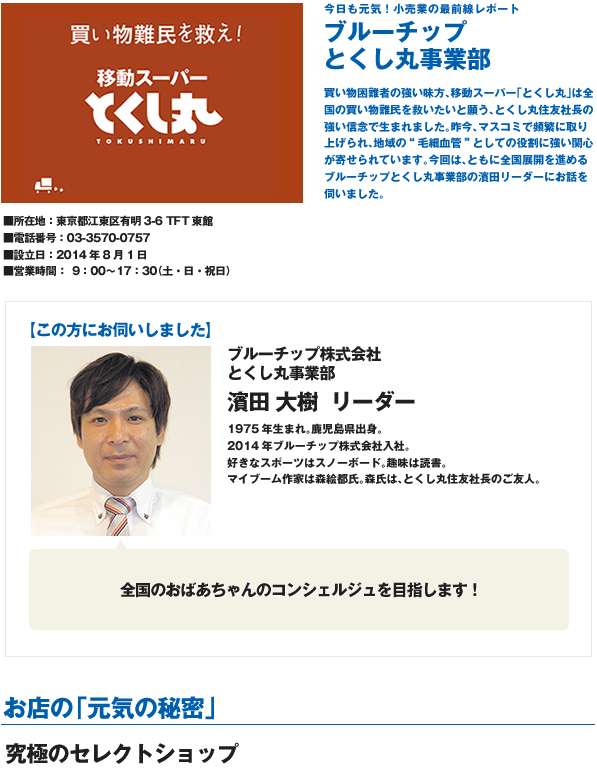
―とくし丸の成り立ちを伺います。
とくし丸は住友社長が当初2人で立ち上げました。4年ほど前、社長のご両親が買い物に困っていたことがそもそものきっかけです。近所のスーパーが潰れたことに加え、病気がちで遠出ができないというご両親を買い物に連れて行ったところ、何万円分も購入してしまい大変心配したそうです。住友社長はそのとき、そうでもしないと食材の調達がままならない人たちが多くいることに気づかされたとのことです。
―とくし丸の特徴について。
とくし丸は委託販売なので、仕入れが発生せず在庫リスクがありません。スーパーの委託で商品を販売、在庫はスーパーに戻して販売手数料が支払われます。また、販売車は、決まった場所に停車し、来ていただくのではなく、お困りの方の玄関前までお伺いします。さらに、宅配と違って実際に商品を見て、触って、確かめて、お買い物を楽しんでいただけます。欲しい商品の注文もできますし、とくし丸ならある程度納得したものを自分で選べます。そこにお客様の高いニーズがあると思っています。
―ブルーチップの役割については。
買い物難民は、郊外型のGMSなど大型小売業に押されて、地元の小さな小売業が衰退していくといった構図の中で発生しています。そうした状況下では、ナショナルチェーンと組むよりも頑張って地域の支えになっているスーパーさんと組んでいきたいという住友社長の考えもあり、全国展開するにあたって、同じく地域小売業をお手伝いするブルーチップということになりました。
―「とくし丸」「ブルーチップ」「販売パートナー」「スーパー」の関係をご説明ください。
まず、とくし丸とブルーチップは一体と考えて本部とします。ですから販売パートナーさんとスーパーさんとの3者の関係となります。まずスーパーさんは販売パートナーさんに商品の販売を委託して販売手数料を支払います。本部は販売パートナーさんに顧客情報の提供、つまりルート開拓を行います。本当に困っている方をつないでルートにしていく作業は地道ですが、これが本部の重要な仕事です。

―販売パートナーさんのルート数は?
1週間に月木、火金、水土に分けて3本のルートを2日ずつ回るのが基本になります。3日に1回新鮮なものをお買い物していただくという考え方です。
―そのルート開拓は大変ですね。
現在、とくし丸導入について100社ほど意思表示をいただいているので、東京の本部だけでは間に合いません。現地の有志の企業さんに地区本部という形でルート開拓などの本部機能を持っていただき、すでに現在全国4か所ほどで始めています。

―見守り役の側面についてご説明ください。
基本的には週2回訪問しますが、いつものお客様が元気がないとか、玄関先に出て来られないとか、異変を感じる場合、地域の包括センターや福祉課などに対処していただくという形で、連絡先と対応方法を取り決めています。さらに緊急の場合には、警察や消防に通報しますが、どうしても住居に入らなければならない状況の時は、ご近所さん立会のもとに行う、といった配慮も必要です。こうした一連の事柄について、事前に販売パートナーさんと自治体との間で協定を結んでおきます。

―思い描くとくし丸像について。
すでに類似の企業も出てきているので、いちはやくメジャーになるようにしたいですね。まずは5年で500台を達成して、将来的には1000台2000台と増やし、「とくし丸」といえば日本全国の人が知っている、いつも全国どこかを走っているという状況を早く作っていきたいと思います。商品の幅を広げて「おばあちゃんのコンシェルジュ」になり、快適に楽しく生活を送るための生活必需品やサービスなども供給していけたらと思います。